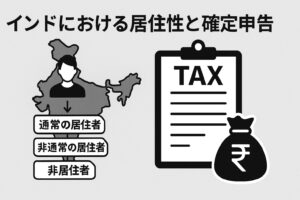3-2-1. 売掛金の水増し
私はX社で経理マネージャーとして勤務していた。X社の日本人駐在員は1名で、支払手続きの最終承認者である。彼は外出が多く、忙しさから内容をほとんど確認せずに承認を行っていた。そのため、会社口座から自分の管理する銀行口座へ送金することは比較的容易だった。もちろん金額によっては発覚の可能性があるが、数万ルピー程度であれば気づかれないだろう。
問題は、その不正送金を会計上どのように処理し、監査から隠すかである。外部監査が定期的に入るため、発見されにくい方法を考えた。
私は、不正送金時に売掛金を増やす仕訳を行った。たとえば10,000ルピー送金した場合、次の通りである。
(借方)売掛金 10,000 / (貸方)現預金 10,000
この処理は本来極めて不自然で、「顧客に支払いをして売掛金を増やす」ことになる。顧客に返金するケースは稀にあっても、売掛金が増えることはない。しかし、この方法には損益計算書に影響を与えないという利点がある。日本人駐在員は毎月の損益を重視するため、費用の増加には敏感だが、この方法であれば細かく調べられる可能性は低い。
もっとも、この仕訳を放置すればいずれ監査人に発見される。そこで利益が十分に出ている月を狙い、次の仕訳で処理を消す(日本人駐在員の承認は得ずに処理)。
(借方)貸倒損失 10,000 / (貸方)売掛金 10,000
こうして一時的に計上した不自然な売掛金を消す。大口顧客を使えば、多少の貸倒損失は許容されやすい。「なぜ貸し倒れたのか?」と問われても、「クレーム対応」や「税務上の問題」といった理由で説明すれば深く追及されないであろう。
コンサルタントの見解
この事例は、そもそも現預金管理が不十分であることを前提としている。現預金管理は不正防止の第一のフィルターだが、完全な管理は難しいため、第二のフィルターを会計処理面に設ける必要がある。複式簿記では、現預金の増減は必ず他の勘定科目に影響する。その「他の科目」に注目して監視すべきであり、今回は売掛金が対象となる。
売掛金の水増しを見抜くためには、以下の分析が有効である。
- 売掛金回転期間の分析
計算式:月末売掛金残 ÷ 当月売上(税込) = 売掛金回転月数
通常、1.5か月程度が正常値。大きく乖離すれば水増しの可能性がある。 - 売掛金の年齢分析(エージング)
発生時期別に売掛金残高を顧客ごとに確認し、支払遅延の有無を把握する。 - 顧客への残高確認
顧客が認識する買掛金残と自社の売掛金残は一致するはずであり、不一致は水増しの兆候となる。
水増しされた売掛金が長期間残れば発見は容易だが、一旦貸倒損失として処理されると表面上は正常に見える。したがって貸倒損失の発生時には経営陣の承認を必須とし、顧客への直接確認を行うルールが望ましい。経営陣は安易に承認せず、「貸倒損失を認めることは、不正を完全犯罪にする可能性がある」ぐらいの意識を持つべきであろう。