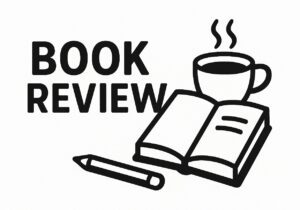3-5-0. 従業員への仮払金
従業員への仮払金とは「子供のお使い」のようなものだ。母が「かっちゃん、ちょっとスーパーにお使い行ってきて。人参、玉ねぎとジャガイモを買ってきてくれないかな?」と言って1,000円を子供に渡す。この1,000円が仮払金である。つまりいくらか明確な金額は分からないけど、大体これぐらいであろうという金額を渡して必要なものを買いに行かせるのだ。そして買い物から帰って、買ってきた野菜、領収書とお釣りを母に渡す。これで仮払金は精算されるのだ。
ビジネスをしていると従業員が仮払いを要求してくるケースがある。例えばインド人従業員がちょっとした文房具をマーケットに買いに行く時や長期で出張をする時は結構仮払いを要求してくる。
社内で使うA4用紙がなくなったから、現金出納担当者が必要な手続きに基づいて、金庫から1,000ルピーを従業員に仮払いし、A4用紙をマーケットに買いに行かせる。そして買いに行った後に領収書とお釣りを現金出納担当者へ渡し、経理部門が記帳する。もし仮払いした金額が不足していた場合、仮にA4用紙が1,200ルピーであれば不足分200ルピーを買い物に行った従業員に支払って精算し、経理部門が記帳する。
インド人従業員が長期で出張する場合も同様で、従業員に仮払いをするケースがある。この場合も出張後、従業員は領収書と残高分(=仮払金額-出張で使用した金額)を現金出納担当者に渡し、経理担当者が記帳する。もし出張で使用した金額が仮払金額よりも多額の場合は、逆に従業員に差額分を支払う。
日本人にとっては当たり前のやり取りである。別に何のリスクもないように思えるかもしれない。しかし日本人にとって当たり前のことが、インド人にとって当たり前にしない又はできない場合がある。
仮払いの手続きをせずに会社のお金を持ち出したり、お使いが終わってもお釣りを現金出納担当者へ返さなかったり、購入するべきものを購入してこなかったり…まともにお使いも出来ないのかと思ってしまうことがある。
しかしふと思い出すことがある。私が小学生の頃、父から500円玉を渡され
「これでタバコを一個買ってきてくれ。銘柄は何でもいいから」
とお使いを頼まれたことがあった。自動販売機で購入し、お釣りと一緒に“タバコ”を父に手渡した。そして父は手渡された“タバコ”を見て私にこう言った。
「ありがとう。でもこれタバコじゃないんだよ…」
と。そして私はこう答えた。
「『明るい家族計画』って書いてあったから、それを選んだのに…」
案外、お使いって難しいのかもしれない。