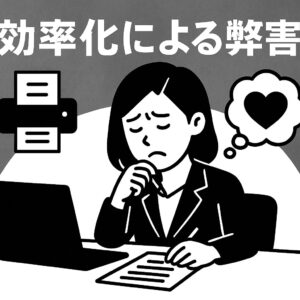3-1-4. 小切手の不正流用
私はX社で小切手の管理および経費処理を任されていた。X社の支払手段はインターネットバンキングではなく、小切手であった。その理由は、インターネットバンキングでは支払先の確認が非常に難しいからだ。
小切手であれば、必ずサインの前に請求書と「支払先会社名」「支払金額」を照合することになる。インターネットバンキングでは、たとえ「支払先会社名」を間違えても、銀行コードと口座番号が一致していれば支払いが実行されてしまう(3-1-3 預金の不正流用参照)。一方、小切手は支払先名が間違っていれば銀行でエラーとなり、支払いは行われない。つまり小切手は銀行側でもチェック機能が働くため、不正防止力はインターネットバンキングよりも高い。
しかし初代社長が帰任し、新社長が赴任した頃にはビジネスの状況が変わっていた。当初は月末に20枚程度の小切手へサインすれば足りたが、業務拡大に伴い50枚以上に増加。さらに社長は多忙となり、外出が増えて請求書と小切手を照合する時間を確保するのが困難になっていた。
そこで私は架空の請求書を作成して経費処理を行い、小切手を準備した。そして新社長が忙しい月末を狙い、多数の支払手続に紛れ込ませた。新社長は「支払先会社名」と「支払金額」を一瞥するだけで、次々とサインしていった。その中に不正な小切手が含まれていることに気づくことはなかった。
コンサルタントの見解
日本で生活していると、書類にサインする機会は限られている。サインと言ったら生命保険への加入、賃貸契約、車の購入、婚姻届ぐらいだ。多くの場合、蟻ぐらいの小さな字で書かれた契約内容を熟読せず、相手の説明を信頼してサインしてしまう。相手を信頼し、将来のトラブルを全く想定していないからだ。
しかし、もし悪意を持った人物が小切手へのサインを求めてきたらどうだろう。従業員が不正を企てているか否かは事前には分からない。だからこそ性悪説に立ち、「不正をする可能性がある」と想定してサインに臨むべきだ。
では、多数の請求書をどうチェックすればよいか。例えば1回につき25枚程度であれば丁寧に確認できる。月50枚の小切手が必要なら、15日と月末の2回に分けて処理すればよい。月100枚なら4回に分ければよい。要は月1回にまとめて処理するから確認が甘くなるのだ。支払処理を平準化すれば、チェックの精度は上がる。
また毎月定期的に支払っている取引先は比較的リスクが低い。継続的な取引に基づく信頼があり、万一過剰支払いがあっても次回で調整できる。したがって、そのような支払先は最低限の確認にとどめ、新規や不定期の取引先に関しては請求書だけでなく発注書との突合も行うべきだ。これにより限られた時間でも効果的かつ効率的なチェックが可能になる。
もちろん、すべての取引先を完全に把握するのは難しい。それでも小切手にサインする際は機械的に確認するのではなく、「この支払先とはどんな取引だったか?」と一瞬考えてほしい。支払先名と購入内容を口に出すだけでもよい。それが潜在的に記憶され、不正を察知するアンテナが徐々に研ぎ澄まされる。さらに支払依頼をしてきたインド人に「この支払ってなんだっけ?」と一言、質問するだけでも牽制機能が働くであろう。
サインには常にリスクが伴う。誰もがそれを理解しているはずだが、信頼する人物から頼まれると、内容を確かめずについサインしてしまう。結果として、知らぬ間に高額な壺を買わされたり、借金の保証人になったりすることもある。ただあまり将来のリスクを考えすぎると、婚姻届にもサインを躊躇してしまうかもしれないが…。