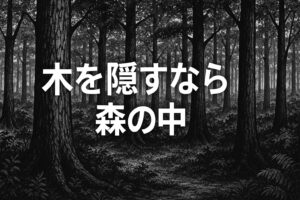3-1-3. 預金の不正流用
私は会社の預金支払データ作成を担当していた。支払は小切手ではなくインターネットバンキングで行われ、その手続きは以下のとおりであった。
- 私が支払データを作成(必要情報:①支払先名、②銀行名・口座番号、③金額)。
- 経理マネージャーが支払データと請求書等を確認。
- 日本人駐在員が同様に確認し、承認。
経理マネージャーは確認用、日本人駐在員は承認用と、それぞれ別のパスワードを持ち、両者が入力しなければ支払は完了しない仕組みであった。しかし、この手続きには2つの大きな盲点があった。
1つ目:銀行は支払先名を照合しない。銀行名と口座番号さえ正しければ、支払先名が間違っていても送金は実行される。つまり、①支払先名に取引先名を入力し、②銀行名と口座番号を自分が管理する口座に設定すれば、銀行からの問い合わせもなく資金を自分の口座へ送金できる。
2つ目:経理マネージャーは①支払先名と③金額は確認するが、②銀行名・口座番号までは逐一見ていない。日本人駐在員は経理マネージャーが厳密に確認していると信じており、実際はほぼノーチェックで承認している。
この穴を利用し、まずは少額でテスト送金を試みた。目的は「問題なく送金できるか」と「取引先から督促が来ないか」を確認するためだ。少額なら誰かに指摘されても「誤送金だった」として即返金すれば、言い訳も立つ。
試みは成功した。資金は問題なく振り込まれ、少なくとも2か月は取引先から督促が来る気配もない。これで、いつでも会社の資金を自分の口座へ送金できる環境が整った。「なりすまし詐欺」のように、取引先を装って口座変更依頼を行えば、不審に思われても説明がつく。 とりあえず不正送金した少額は会社口座へ一旦返金し、その後の会計処理も含め、より綿密な計画を立てることにした。絶対にバレないようにするために。
コンサルタントの見解
パソコンとインターネットの普及で、私たちの生活は格段に便利になった。かつて手書きだった書類はパソコンで作成でき、郵送していた文書はEメールで瞬時に送れる。銀行に行かなくてもクリック一つで支払ができ、家にいながら買い物もできる。ほぼあらゆる行動が効率化された。
しかし、効率化は常に良いことだろうか。たとえばラブレター。手書きなら、言葉を選び、書いては破り、何度も推敲する。時間はかかるが、その分想いは込められる。パソコンなら不要な箇所を消して打ち直すだけで済み、効率的に原稿は完成する。今ならChat GPTが彼女のハートを鷲掴みする文章を作ってくれる。しかしラブレターをプリンタでプリントアウトし、それをそのまま渡す人はいないであろう。なぜならラブレターの目的は単に気持ちを伝えることではなく、相手の心をつかむことだからだ。プリンタで印刷された無機質な手紙より、多少汚い字であっても時間をかけて手書きしたほうがよっぽど好印象なはずだ。
仕入先への支払も同じだ。目的は「正しい相手に、正しい金額を支払うこと」。その目的達成のためには、効率化すべき部分とそうでない部分を見極めなければならない。すべての作業を効率化したい気持ちは分からなくはないが、目的達成の確率を下げるような効率化は避けるべきだ。「どこは効率化してよいのか」「どこはあえて時間をかけるべきか」――今一度、見直してほしい。