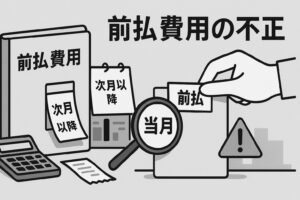3-3. サービスの輸出入に関するGST
サービスの輸出入に関するGSTも基本的に考え方は同じである。原則は「サプライヤーの州」及び「Supplyが行われた州」を検討することになる。
「サプライヤーの州」はそんなに難しくないだろう。輸入の場合は海外になるし、輸出の場合はインド国内となる。
問題は「Supplyが行われた州」である。輸入と輸出を分けて説明しよう。
サービスの輸入
「Supplyが行われた州」は原則サービスを受けた者の場所で判断されるため、インド国内になる。また当然サービスはインド国内で消費されるため、GSTの課税対象となる。例えば、親会社へロイヤルティ又は技術支援料を支払う場合はサービスの輸入に該当する。
サービスの輸入の場合、どのようにGSTを納めるのかが問題となる。通常だとサービスの享受者が提供者にGSTを払い、当該提供者がGSTをGST当局に納める。しかしサービスの輸入の場合、そういうわけにはいかない。なぜならサービスの提供者はインド国外であるため、実務的にインドGST当局に納税することは難しい。そのためReverse Charge Mechanism(以下RCM)というスキームでGSTを納税する。
RCMと特別な単語が出てくるとなんか構えてしまうかもしれないが、なんてことはない。考えようによっては物品の輸入と同じようなスキームである。要するにサービスの享受者が、自らGSTを計算し直接GST当局に納めるだけである。このことをちょっと特別扱い的にカッコつけてRCMと呼んでいるだけだ。RCMで納めるケースはサービスの輸入のほかにもあり、専門家との会話の中で結構頻繁に出てくるので覚えておくのが良い。
RCMで注意して欲しいことがある。RCMが適用される場合、仮払GSTから充当する処理は出来ず、必ず納税しなければならない。そして納税後に納税したGSTは仮払GSTとして使用することが認められる。仮払GSTに関しては別途詳しく説明する予定だが、ここでは仮払GSTに関する取扱いが少し異なるとだけ覚えて置いて欲しい。
もう一つ注意していただきたいことがある。それはShecule I(4)の内容だ。Schedule Iには無償でもGSTを課税する取引が列挙されている。そのうち(4)を覚えて置いていただきたい。
(4)Import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India, in the course or further of business.
要するに海外にある特別な関係を有する者(例えば海外グループ会社)から無償で提供されたサービスに関してGSTを課税するということだ。この条文が根拠で、今話題になっている「日本人駐在員費用のGST課税」の問題が発生している。この問題に関して、全体的なGSTの説明が終わった後に言及していこうと思っている。
サービスの輸出
サービスの輸出であるかどうかは「Supplyが行われた州」で検討する。「Supplyが行われた州」がインド国外であればサービスの輸出に該当しGSTは無税となるが、インド国内であればGSTが課税される。「Supplyが行われた州」の判断は、3-3. Supplyが行われた州(サービス)を参考にして欲しい。
法律に照らし合わせて判断することは最終的に大切な事であるが、まずは原則に戻り「提供されたサービスがどこで消費されたか?」も考えて欲しい。インド国内か?インド国外か?インド国内であれば、GSTが課税される可能性があるし、インド国外であればGSTが課税されない可能性がある。法律に列挙されている事例は、あくまで事例であり実務上の全ての取引をカバーしているわけではない。そのため列挙されていない取引が生じた場合は、列挙されている事例から取引内容及び法律の趣旨を考えて判断しなければならない。当然、契約書の内容を作成する時にも注意する必要があるだろう。契約書上、提供されたサービスがインド国内で消費されることを目的とするような一文が含まれているとGST当局はそこに目を付け、サービスの輸出を否認してくるリスクが発生する。
次回、仮払GSTの説明をする予定である。